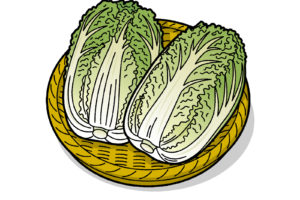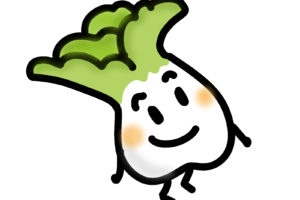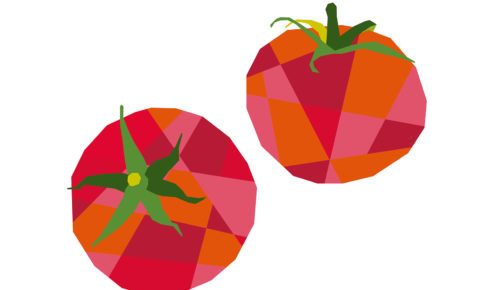長芋をすりおろした時に、気が付いたらとろろがピンク色になっていて

と焦った思い出がある私。
長芋初心者の頃は、赤(ピンク)→黒っぽく変色するとろろを見て


と思っていました。
そんなビクビクした気持ちも最初だけ。月日が経つにつれ、いつの間にかそんな心配も吹っ飛んでいました。
長芋大好き家族のために、しょっちゅう食卓に長芋を並べていたんです。すると、高確率で長芋が変色しちゃいます。
見慣れてしまうと

という気持ちになるものですね。
でも…毎回同じように長芋を扱っているつもりでも、同じように変色するわけではないんです。


そんな疑問を解決すべく、今回は長芋の変色のヒミツに迫りたいと思います。
- 長芋が赤く変色しても食べられるのか?
- 長芋が赤く変色してしまう理由
- 長芋の変色を防げる身近な調味料とは?
- 新鮮な長芋の見分け方
- 長芋の適切な保存方法
- 長芋の食べごろと収穫時期
長芋は変色しても食べられる!

購入してすぐに調理したのに、

そうなるとビックリしてしまいますよね。そして一番の心配は、食べられるのかどうか…。
結論から言います。安心してください、食べられますよ!
なぜ長芋が変色しても食べられるのか?それは酸化とポリフェノールが関係してくるのです!
長芋の酸化
あなたは、皮をむいてから少し時間が経ち、黒っぽくなってしまったリンゴを食べますか?
食べると答える人が多数派かと思います。
実は、長芋の変色はリンゴが黒くなるのと同じ仕組みなのです。切り口が空気と触れて変色するこの現象を酸化と言います。
リンゴの酸化は頻繁に起きる出来事ですね。ちょっとぐらい色が変わっても、気にせずに食べちゃいます。
長芋の酸化も同じ仕組みです。ちょっとぐらい色が変わっても、気にせずに食べちゃってOK!
なんだかホッとしました。
いくら食べられるからとは言え、酸化して変色した部分は体に悪そう…。果たして、私たちの体に悪影響はあるのでしょうか?
長芋とポリフェノール
長芋の切り口が空気に触れると酸化し、変色します。
空気と反応しているのは、長芋に含まれているポリフェノールです。
ポリフェノールは決してワインだけのものではありません。ほとんどの植物に含まれる成分なんです。
ポリフェノール自体は健康に良い成分です。酸化が発生した後でも、体に悪影響を及ぼすことはありません。食べても問題のないものなので、安心してください。
スポンサーリンク
長芋の変色はお酢で防止

長芋の変色を防ぐには、食べる直前に調理してしまうのが一番良い方法です。
とは言っても、料理が出揃って食べ始めるまでに、どうしても時間がかかってしまいます。
そんなときは、お酢を使って長芋の変色を防止しましょう!
- 500㏄の水に小さじ2のお酢を入れる
- 皮をむいた長芋を10分程度漬けておく
たったこれだけで、変色が防げます。
また、お酢に漬けることで長芋によるかゆみ対策にもなります。手のかゆみまで予防してくれるなんて、お酢ってすごいですね!
余った長芋にもお酢を使おう!
使い切れず残っている長芋の保存方法です。ここでもお酢が大活躍!
- 切り口に酢水をつける
- ラップをする
- 冷蔵庫に入れる
お酢につけてあげると、変色防止しつつ冷蔵保存ができますよ。
一方私は、長芋を全部一気にすりおろすタイプなのです。食べきれない分は冷凍保存します。
冷凍保存のときも、少量のお酢を入れると効果的です。ジッパー付きの袋に密閉して、冷凍庫に入れましょう。
変色した長芋の活用法
もし長芋が変色してしまったら、すりおろしてお好み焼きのつなぎにしたり、おやきにして焼いてしまいましょう。
もう一つ別のパターンもご提案。
半月切にし、ポン酢やオイスターソースで味付けて炒め物にしましょう。食感が残ったまま楽しめておいしいですよ〜。
長芋の選び方

長芋の変色は自然に起こる現象、ということがわかりました。でも、やっぱり黒く変色した長芋より、白くて新鮮な長芋が食べたいですよね。
そのためにも、まずは鮮度のよい長芋選びをしましょう。
カットされている長芋
カットされてパックに入っている長芋は、切り口からヒントを得ます。
切り口に赤い斑点や黒ずみといった変色がないかを確認。白くてみずみずしい長芋を選びましょう。
形は太い物がおすすめです。細い長芋はアクが強いことが多いので避けましょう。
丸ごとの長芋
長芋の表面に、黒っぽいシミや傷がないか確認しましょう。肌色でツヤがあるものを選ぶと良いです。
形は、太くて真っ直ぐに伸びている長芋を選びましょう。ズシッと重たいものなら尚良しです。
オガクズがついている長芋は

と思いがちです。しかし、これは長芋を丁寧に扱っているという証拠なのです。
長芋を空気に触れさせないための工夫なので、オガクズがついているものは積極的に買ってみるとよいでしょう。
続いては、買ってきた長芋の保存方法をご紹介します。
スポンサーリンク
長芋の保存方法

買ってきた新鮮な長芋を変色させないために、正しい方法で保存しましょう。
カットされている長芋
パックを開けると酸化・乾燥し始めてしまいます。調理するまでそのままの状態で、冷蔵庫に入れておきましょう。
丸ごと買った長芋
オガクズが付いているならそのまま、付いていないなら長芋を新聞紙に包みましょう。
そして、風通しの良い冷暗所で保存します。夏場は冷蔵庫に入れておくと安心ですね。
長芋は夏に収穫すると変色しやすい?

長芋のポリフェノールに含まれているドーパミンは、細胞の活発な長芋の先端部分に多く含まれています。
特に、夏場は細胞分裂が盛んでアクが強くなります。
そのため、夏場に収穫せず、秋に掘るのが一般的なのです。
長芋はスーパーで一年中見かけるので、収穫時期が秋というのはなかなかピンときませんよね。
どうして長芋は一年中買えるようになっているのでしょうか?
長芋の収穫は年に2回
長芋の植え付けは5~6月です。それに対して収穫は、“秋掘り”と“春掘り”の年2回シーズンがあります。
まず、初めに収穫するのは“秋掘り”。
夏場は細胞分裂が盛んで、変色のリスクが高くなります。その時期を越えた秋が一番初めの収穫時期です。
秋掘りは11月初旬~12月で、この時期に全体の6割程を収穫します。残りの4割の長芋は、土の中に残しておいて自然貯蔵します。

この残しておいた長芋は、土の中で冬を越えます。そして4~5月に“春掘り”として土の中から収穫します。
先に秋掘りした長芋は、土付きのまま冷蔵庫に入れて、眠らせた状態を保ちます。そして春掘りまでの間、順に出荷しているのです。
11~3月の5ヵ月分の長芋は冷蔵庫で保存。
4~10月の7カ月分の長芋は土の中で貯蔵して順に出荷。
これが、1年中長芋が流通している仕組みだったんですね。
長芋の食べごろは冬!
11~12月の長芋は、皮が薄くみずみずしいので、食べごろなんです。
とはいえ、農家の人の話では

とのこと。
確かに!我が家も夏バテ防止に食べることが多く、冬はなかなか食べません。

なんとなく、長芋は夏が旬の食べ物だと思い込んでいた私なのでした。
スポンサーリンク
まとめ
- 長芋が赤く変色しても食べられる
- 長芋は切り口とポリフェノールが酸化して変色する
- 長芋にお酢をつけると変色を防げる
- 太くてまっすぐ伸びている長芋を選ぶべし
- 長芋は冷暗所で保存するべし
- 長芋の食べごろは冬
今までは

なんて言っていた私ですが、子供が


なんて覚えて育っちゃったら恥ずかしい!
これからはお酢を上手に使って、長芋本来の色を食卓に並べたいと思います。
でも、変色していても抵抗なく食べられる我が子が、少々たくましく思う気も…。
我が家の食卓では、長芋と言えば夏!でしたが、今年は冬に長芋を食べて、みずみずしさを堪能したいと思います!
今年はお鍋と共に、冬のとろろごはんを味わってみてはいかがですか?